TopPage ->
ジェラルド・ブレット『イギリス短詩選集』(1933年)序文
■ジェラルド・ブレット『イギリス短詩選集』(1933年)序文
(Gerald Bullett, The English Galaxy, 1933, Preface )
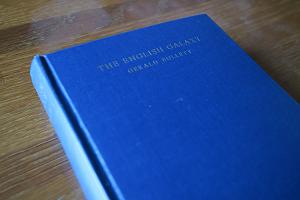
訳文
すでに多くの英詩選がある中へ、あらたに一つ加えようとするにあたっては、形式だけの前書きでは足りぬだろう。今はまだ推敲を重ねつつあるこの本を上梓する価値を、わたくしは少しもうたがってはいない。「The Golden Treasury」「The Oxford Book of English Verse」という大著は、文学史にのこる記念碑である。また単に記念碑であるだけでなく、わたくしたちみなの永遠の財産である。しかし、これらの著作があるからといって、この著者以外のわたくしたちが、英詩を少しことなる角度からとらえ、範囲をしぼった形の詩選集を編むことが、否定されるいわれは少しもない。短い詩というものに着目するならば、英詩のはじまりから1900年までの歴史全体を網羅する本格的な詩選集はいまだなかった。この「ENGLISH GALAXY」では、他の詩選集では扱われてこなかった300あまりの詩を収録した。(英詩という黄金の分野をきりひらいた先人の業績と研究に負うところは計りしれない)率直に名づけた本書の題名に、特別な説明は不要かと思う。
「英詩のはじまりから1900年まで」という説明には採集の範囲がしめされている。20世紀の作品が1つ2つ含まれているが、その詩人の業績が20世紀がはじまるまでに確立していたからである。作品の選択にあたっては、3つの簡単な規則にしたがった。
(1)「クーブラカーン」より短いこと。
(2)単に内省的、描写的ではなく、リリカル(叙情的)であること。そして短く、かつ短すぎぬこと。とはいえ忘れてはならぬのは、リリカル(叙情的)を狭義にとらえないこと。単に短いというだけでは詩にはならない。
(3)確立した評価に盲従してはいけないし、個人の好みから独断に走ってもいけない。どちらの偏りもさけること。
1つ目の規則に根拠はない。2つ目の規則は、詩の衝動の本質をどのようにとらえるかということであり、この説明で読者をわずらわせるつもりはない。3つ目の規則にのみ少し説明をくわえよう。あらたに詩選集を編もうとするものが、文学史が作品に下した評価を軽んずるなどということはしないであろうが、もしそのものが先人の評価に盲従し、みずからは価値を感じることのない作品までも、その詩選集に採録するのであれば、そのものは非常に大きな虚偽の罪を負わねばならない。極言するならば、たとえどれほど伝統を重んじようとも、自らが好むものを選び、好まぬものをふるい落とさねばならぬ。たとえわずかであっても、編者の意思が表現されているのでなければ、その詩選集にはなんの意味もない。
厳密ではないが、作品はほぼ詩人の生誕の順に並んでいる。作者が不明の作品は、読者およびわたくしの便宜のために、他とは分けて、一人の作者のように先頭にまとめて配置した。ごく一部の作品をのぞき、作品は全文を掲載した。2,3の作品では、余計な行を取りのぞくほうが、妥当であるし望ましいとわたくしは考えた。さらにわずかであるが、全文を掲載するには長すぎる詩から、リリカル(叙情的)な行を抜粋したものもある。削除した例として、「Mary Morison」の第3句がある。わたくしが思うにこの部分は、単に表現がよくないというだけでなく、前の句までの、悲しみのかざらない表現のあと、最後の句によって、全体の詩情までもが、すっかり台なしになってしまっている。
O Mary, canst thou wreck his peace,
Wha for thy sake wad gladly die?
Or canst thou break that heart of his,
Whase only faut is loving thee?
If love for love thou wiltna gie
At least be pity to me shown:
A thought ungentle canna be
The thought o' Mary Morison.
長い詩からの抜粋の例は、「LangLand」からの17行がある。このようにしなければ、紹介されることはなかったであろう。他に、チョーサーによる「Romaunt of Rose」からの抜粋、ジョン・デイビスの「Orchestra」の冒頭からの抜粋がある。このようなみのほどしらずの行いも、成功すればみとめられ、失敗すれば断罪される。わたくしが取った方針には理解をいただき、それぞれの部分については失敗がないかを審判いただきたい。同様のことがつづり字と句読点にもあてはまる。長い年月の間に、先人たちがその詩選集の中で実践してきた方法から、わたくしが学んだことは、一般読者の利便を優先することだ。句読法の本来の目的はよみやすくすることである。文法への忠誠も、よみづらくなるのであれば誤りである。しかしながら、つづり字の扱いは単純な問題ではない。現代つづり字へと機械的に書きかえることもできなくもないが、原文の趣きや色彩はうしなわれてしまう。現代つづり字で書かれた「失楽園」を、初期のテキストを収録したオックスフォード版と比べてみると、この困難が見えてくる。19世紀はあきらかに、行きすぎたつづり字の見直しが、無差別におこなわれた時代である。これにより最も甚大な被害を受けたのがシェイクスピアで、わたくしが見つけたのは少なくとも1ヶ所、他にも同様のものが多数あるはずだ。つづり字の訂正という名のもとに、もともとの適切な単語が、明らかに誤ったものへと置きかえられてしまっている。
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his height be taken.
上記はソネット116番17、18行目の標準テキストである。クオート版では以下となっている。
It is the star to every wandering bark,
Whose worth's unknown, although his higth be taken.
ここにある「Higth」はおそらく「Hight」「Height」の誤植だと考えられる。(わたくしたちの父親世代が見たら喜んだにちがいない。)しかしながら、「Highth」という語は、ミルトンの詩にしばしば見うけられる。加えて「worth」との韻の関係もある。「height」の耳障りな調子をさけていて、やわらかな響きをもたらしている。この例は、現代つづり字の行きすぎた適用には大きな危険があることを示している。同様に、原文がもつ新鮮さや趣きが失われてしまう危険もある。しかしながら、16世紀から17世紀の写本を見たときに、なじみのうすいわたくしたちがそのつづり字に感じるのは、古いものへの魅力である。もともとは、その作品にはなかったものである。古いものへの魅力がある範囲をこえてしまうと、それをみたわたくしたちは、本来の詩の理解から思考がそらされてしまう。このような理由から17世紀以降の作品では、散見される一部の特徴的な単語や、ミルトン、ダンにみられるような充分な文例から詩人独自のつづり字の規則であると判断できる場合をのぞき、現代つづり字で表記することを、やむなしとした。以下のごく初期の詩、「Western wind, when wilt thou blow」「The bailey beareth the bell away」では、すでに広くしられている現代つづり字のテキストから採った。
句読点と全体構成について、2点、説明を加えたい。(1)チョーサーの詩、および初期の詩において、「e」のうえに付された点は、通常は無音の「e」を小さく発音することを示している。ワイアット、ダン、その他いく人かの詩人において、韻律の疑問は残るが、主に強勢される節のいくつかの箇所に、わたくしはアクセントの記号を付した。ワイアットの作品ではこのことがさらに重要である。わたくしは、フォックスウェル女史の信頼できるテキスト、ティリヤード博士による詩人の評論を参照し、トッテルらの詩選集より以前からあるテキストを本書に掲載した。なぜなら、トッテルらのテキストは、編集の際に、あたかもアイロンをあてたかのように、作品のもつ特異さ、悲しさ、恐ろしさのほとんどが、平たくならされてしまっていたからである。あなたのためではなく、あなたの弱い弟のためなのだと、言い訳でもしないかぎり、このような余計な配慮に対して彼は腹をたてたにちがいない。ジェラルド・マンリ・ホプキンスの詩に付されたアクセントについては、わたくしは関与しておらず、オックスフォードプレスから出版された際のテキストに、忠実なものであることを補足しておく。(2)多くの詩には題名を記していない。詩人の名は、上部ではなく下部にしるすという本書の構成について、読者から理由をもとめる声があるかもしれない。しかしながら、読者の方々はわたくしが考えたこの構成を、受け入れ、賛同してくれるはずだと信じている。詩の一行目は、詩がもって生まれた題名だといえる。美しさや意味の理解のために必要だと考えた場合のみ、わたくしは題名をふくめることにした。さらにいうならば、詩選集に付された題名のほとんどは、詩人ではなく、編者が思いついたものだということを忘れてはいけない。題名であれ、日付であれ、解説であれ、作者であれ、何ももちこまず、ただ詩だけと向き合うことがわたくしのねらいである。それぞれの作品が、いつ誰によって書かれたか知りたいと思うのも当然であるが、どれほど過小に考えても、詩人の名よりも、大切なのは詩そのものである。詩人の名前は下部にあり、日付は索引に掲載されており、参照にあたっては何の不都合もないはずだ。熟慮の上で、文中にはいっさい付注もおこなわなかった。
本書への掲載にあたって版権の利用を快く承諾いただいた詩人、出版社、版権者の方々への謝意の代わりとして、以下にその名を掲載する。
Edmund Blunden, and his publishers, R. Cobden-'Sanderson Ltd, for certain poems by John Clare first printed in their edition of that poet;
the Executors of Robert Bridges, and the Clarendon Press, for nine poems by Robert Bridges;
Little, Brown and Co, Boston, U.S.A., for four poems from the Centenary Edition of the works of Emily Dickinson, edited by Martha Dickinson Bianchi and Alfred Leete Hampson;
the Executors of Thomas Hardy, and Macmillan and Co Ltd, for three poems by Thomas Hardy;
Pamela Hinkson for a poem by Katherine Tynan (Hinkson);
the poet’s family, and the Oxford Press, for four poems by Gerard Manley Hopkins;
A. E. Housman for great kindness in respect of five of his Last Poems;
the Executors of George Meredith, and Constable and Co Ltd, for three poems by George Meredith;
Wilfrid Meynell for generously allowing me a poem by Alice Meynell and two poems by Francis Thompson;
George Bell and Sons Ltd for the seven lyrics from Coventry Patmore’s The Angel in the House ;
the Trustees of William Morris, and Longmans Green and Co Ltd, for three poems from The Earthly Paradise;
Lloyd Osbourne for sixteen lines of a poem by Robert Louis Stevenson;
Hcincmann and Co Ltd for a poem and part of a poem by Algernon Charles Swinburne;
the Executors of Herbert Trench, and Constable and Co Ltd, for one poem by Herbert Trench;
William Buder Yeats for a poem from his The Wind among the Reeds (Macmillan), two poems from In the Seven Woods (Macmillan), and one from Early Poems (Benn).
詩を見出し、出版してきた先人に負うところはあまりに大きく、ここでそのすべてを枚挙しきれるものではない。よりよいテキストを参照するための苦労はあったが、この「銀河」を作り上げるまでには、わたくし自身よりも、他の優秀な「天文学者」たちの労によるところが大きい。
クレメント・ロビンソン 「A Handful of Pleasant Delights」
リチャード・エドワーズ 「Paradise Of Dainty Devices」
エドワード・ロリンズ 「The Phoenix Nest」
リチャード・トトル 「Tottel's Miscellany」
フランシス・デイヴィスン 「Davison's Poetical Rhapsody」
これら詩選集は、詩の世界を旅するものには、避けてとおれない場所である。
そして、この序文の冒頭に戻る形となるが、最後にクイラー・クーチ氏の名をあげ、敬意の代わりとさせていただきたい。これらの著作がなかったならば、英詩という街での、大通りはもとより細い路地までの知識は、ごくごく小さいままであっただろう。
脚注
サマセット・モームは彼の「読書案内」の中で読者に薦める詩選集を3冊あげていて、これはその一つ。
詩集としてのたたずまいがとても美しい。ページをめくると小さな銀河が浮かび上がる。
ジェラルド・ブレット (1893-1958) 作家
クレメント・ロビンソン (1566-1584) 詩人
リチャード・エドワーズ (1525-1566) 詩人
エドワード・ロリンズ (1889-1958) 文学者
リチャード・トトル (1525-1594) 編集者
フランシス・デイヴィスン (1575-1619) 詩人
Copyright (C) 2004-2022 YASUMOTO
KITAN